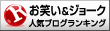ジョセフ・P・ケネディ, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=492863 / CC BY SA 3.0
#在イギリスアメリカ合衆国大使
#アメリカ合衆国の実業家
#アメリカ合衆国の映画プロデューサー
#アメリカ合衆国のカトリック教会の信者
#マフィア
#ケネディ家
#1888年生
#1969年没
ジョセフ・P・ケネディ
ジョセフ・パトリック・“ジョー”・ケネディ・シニア(Joseph Patrick “Joe” Kennedy, Sr.、1888年9月6日 – 1969年11月18日)は、アメリカ合衆国の政治家・実業家、第35代大統領のジョン・F・ケネディの父である。「ジョー」は「ジョセフ」の短縮形。
巨大な資産をバックグランドにした民主党の有力政治家であり、アメリカのカトリック教徒および、アイルランド系アメリカ人の実力者でもあった。フランクリン・ルーズベルトの大統領選出時(1932年)に財政支援を行った功によって、初代証券取引委員会委員長(1934年)、連邦海事委員会委員長(1936年)、在イギリスアメリカ合衆国大使(1938年~1940年)のポストを歴任した。
1888年、ボストンにアイルランド系政治家の子として生まれたジョセフ・P・ケネディ・シニアは、ボストン・ラテン・スクールからハーバード大学に進み、金融業につくと株式市場を利用して莫大な財産を築いた。この財産を元手にさまざまな資産を運用するようになった。第一次世界大戦中、ケネディはベスレヘム・スチール社の造船部門の支配人補佐となり、海軍次官補だったフランクリン・ルーズベルトと知り合った。その後、映画産業に食指を動かし、いくつかの映画会社を統合してRKOを設立する過程で一財産築いた。さらに1933年に禁酒法が廃止されると、ルーズベルト大統領の長男と組んでサマセット社という会社を設立、ジンとスコッチの輸入を一手にとりまとめさらなる富を生み出した。1945年には建設当時世界最大のビルだったシカゴのマーチャンダイズ・マートビルを買い取ったことでも有名になった。
しかし外交官および政治家としての活躍は唐突に終わる。1940年11月、バトル・オブ・ブリテンのさなかに行われたボストン・グローブ紙のインタビューで「英国で民主主義は終わった。米国にはまだあるかもしれない」と発言したことが大問題となったためだった。以後ケネディは表舞台には出ず、豊富な資産を運用して息子たちの政界進出を強力にバックアップした。しかし豪腕で知られたケネディも、1961年に73歳で脳梗塞の発作を起こし、言語と身体が不自由になると第一線を退き、1969年11月18日に家族にみとられながら世を去った。
子供たちには、大統領になった次男「ジャック」(ジョン・F・ケネディ)だけでなく、政界入りさせようとしていたが海軍での軍務中に不慮の死を遂げた長男の「ジョー・ジュニア」(ジョセフ・P・ケネディ・ジュニア)、兄ジャックの下で司法長官をつとめた後に上院議員となり大統領選の予備選最中に暗殺された三男の「ボビー」(ロバート・F・ケネディ)、30歳の若さで上院議員となった末弟で四男の「テッド」(エドワード・M・ケネディ)、スペシャルオリンピックスの創設者の一人である三女、駐アイルランド米国大使を務めた五女がおり、孫には下院議員(ボビーの子)、(テッドの子)など多くの政治家を輩出し、その国民的人気によって一族は「ケネディ王朝」と称された。
ジョー(ジョセフ・P・ケネディ・シニア)は父パトリック・J・ケネディ、母メアリー・オーガスタ・ヒッキーの長男としてマサチューセッツ州ボストンに生まれた。父は実業家であり、アイルランド系アメリカ人コミュニティーの指導者として知られていた。ジョーの祖父パトリック・ケネディは1849年にアイルランドからアメリカ合衆国に移住してきたため、ジョーはアメリカ移住後の三代目であった。移住後、一族はアメリカ社会でのステータスを少しずつあげていったが、依然としてボストンではアイルランド系は上流階級を形成するイギリス系プロテスタント市民(「ボストン・ブラーミン」と呼ばれた)からはよそ者扱いであった。パトリック・J・ケネディは民主党員として1885年にマサチューセッツ州選出下院議員に当選した。
ジョーが生まれたとき、すでにケネディ家は裕福であり、ボストンのみならず東海岸において影響のある一族であった。父パトリックは長男ジョーに期待をかけ、一流校であるボストン・ラテン・スクールに進ませた。同校がボストンのプロテスタント系エスタブリッシュメントの牙城ともいうべき学校であったことから、両親がジョーに対してカトリックの枠にとどまらずに、さらなる社…
powered by Auto Youtube Summarize