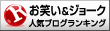内戦, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=1010 / CC BY SA 3.0
#内戦
#歴史の一覧
#軍事の一覧
内戦(ないせん、英語:civil war)とは、国家の領域内で対立した勢力によって起こる、政府と非政府の組織間の武力紛争を指す。
タンペレの戦い後の都市遺跡(フィンランド内戦; 1918年) スペイン内戦(1937年) レバノン内戦(1978年) 「内戦 (civil war)」と「内乱 (rebellion)」は同義に用いられることも多く、厳密な区別はない。
しかし、一般的には、暴動の範囲内である事象を「内乱」と呼び、武力を用いる形態にまで発展した事象を「内戦」と呼んで区別する場合もある。
欧米言語では「civil war」(英語)や「bellum civile」(ラテン語)や「Bürgerkrieg」(独語)というように「市民戦争」「市民同士の戦争」という言い方をする。
ただし近代的な国際関係・国際秩序が形成された1648年のヴェストファーレン条約前の時代では、内戦と対外戦争との区別は明確ではない。
又、政府が倒されて政治体制が転換された場合には、フランス革命、共産主義革命、ルーマニア革命 (1989年)のように、内戦や内乱ではなく「革命」という表記を用いる場合も多い。
内戦と内乱の用語の使い分けは慣習的なもので、明確な区別があるわけではない。
スペイン内戦は「スペイン内乱」とも呼ばれる。
国際法上の位置づけとしても、アメリカ南北戦争では両軍に戦時国際法が適用されたが、ロシア内戦では国際法は無視された。
国家の転覆を意図した者には内乱罪が適用される例が見られるが、内戦の規模が大きくなると、アメリカ南北戦争のように政治的理由から内乱罪の適用が避けられることもある。
植民地の独立戦争などは支配側は「内戦」や「反乱」と呼び、植民地側は「独立戦争」と呼ぶことが多く、アルジェリア戦争のようにアルジェリア側は「独立戦争」と呼び、フランス側は「内戦」と呼んだように、戦争の性質によって内戦かどうか意見が分かれることも多い。
このような場合には、支配者側が交戦相手を国家とは見なさず、相手を戦時捕虜ではなく犯罪者として扱い、捕虜の権利を認めない、犯罪者として処刑したりする事態が発生することも多い。
1989年のルーマニア革命では、国軍と秘密警察という国家機関同士の戦いになり、秘密警察の構成員は全員が非合法組織の犯罪者とされ、死刑、懲役、公職追放などの処罰を受けている。
内戦は、国内の全国政府の座を争うために起こる事象(例:戊辰戦争、国共内戦、イエメン内戦、アンゴラ内戦)の他、民族的(ルワンダ内戦。アメリカ南北戦争やボーア戦争も同側面がある)、宗教的(例:レバノン内戦、第一次・第二次スーダン内戦など)、イデオロギー的(例:スペイン内戦、ニカラグア内戦、エルサルバドル内戦)な衝突などから生じる事象がある。
冷戦下では様々な国外勢力が間接・直接的に介入し、事態を悪化させるケースも多かった。
一時、冷戦後は国際社会は介入に概ね消極的となったが、EUにとっては域内であり歴史的に重要な地域であるユーゴスラビア内戦や、地下資源(ダイアモンド)の利権をめぐって残虐行為が繰り広げられたシエラレオネ内戦のように、冷戦後に悪化するケースも多く、ふたたび国外勢力が介入する場合も多い。
民族的なものについては民族紛争も参照。
独裁政権の国では、民主化要求デモなどの武力を行使しない運動も内乱と規定され武力によって鎮圧されることがある。
内戦が激化した場合、1991年以降のソマリアのように中央政府そのものが事実上崩壊し、無政府状態となる例も存在する。
内戦の原因には様々な説が存在するが、その国の中央政府の統治能力は重要な要因とされている。
経済的な不満や地域的な対立などの不安要素が存在する場合においても、政府の統治能力が高い場合は内戦勃発リスクは大幅に減少する。
政府の統治能力の極端に低い、いわゆる失敗国家において、特に失敗の度合いがひどい場合は暴力の独占が崩れ、各地に軍閥が割拠し内戦が勃発する場合がある。
近代的な国際関係・国際秩序が形成されたおもに17世紀後半以降の内戦のみをあげる。
戦争一覧および独立戦争一覧も参照。
powered by Auto Youtube Summarize