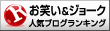住民税非課税世帯とは、言葉の通り「住民税が課税されない世帯」のことです。
ですから、世帯の全員が住民税を免除されるということなります。
また、住民税非課税世帯になりますと、それ以外にもさまざまな優遇措置をうけることができます。
そこで今回は、具体的にどのような優遇措置があるのか、またどのような場合に住民税非課税世帯になるのかになるのか、といったことについてお話したいと思います。
1.住民税非課税と住民税非課税世帯
まず住民税非課税ですが、対象になるには、
① 生活保護を受けている方
② 障害者、未成年者、寡婦または寡夫の方で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収204万4,000円未満)である方
*寡婦(夫)とは配偶者と死別若しくは離別した独身の方の事
③前年の所得金額のが35万円以下(給与収入で100万円以下)である
この3つのうちの どれか1つに当てはまればよいということになります。
では次に、住民税非課税世帯の対象はどうなるかと言いますと、「世帯の全員が住民税非課税であること」ということになります。
なおここで言う「世帯」とは、生計を一にしている人たちということで、単に一緒に暮らしているだけで、生計を同じくしていない場合は同一世帯にはなりませんので注意してください。
で、この③についてですが、生計を同じくする世帯の人の数によって、この金額は緩和されます。
つまり、前年の所得がこれより多くても、住民税非課税世帯になることができるんですね。詳しくは、後ほど説明します。
2.どのような優遇措置があるのか?
住民税非課税世帯になりますと、当然のことながら「住民税が免除される」という恩恵が受けられるわけですが、それ以外にも、実に様々な優遇措置を受けることができるんですね。
しかし必ず受けられる恩恵と、お住まいの自治体によって受けられない恩恵がありますので、注意が必要です。
まず必ず受けられる恩恵をまとめますと
①NHK受信料の免除
これは住民税非課税世帯で、かつ世帯のだれかが障害者の手帳を持っていれば「NHK受信料」の受信料が全額免除になるというものです。
②高額療養費制度利用時の自己負担額が少額
高額療養費制度とは、入院や手術などをして医療費が高額になった時に自己負担金額を軽減してくれる制度です。
住民税非課税世帯になりますと、医療費の自己負担の上限額(1ヶ月当たりの)は、35,400円までになります。
また、70歳以上であれば24,600円まで、とさらに減額されることになっています。
③保育料・高等教育の無償化
まず保育料ですが、0歳から2歳までの子どもについて保育の必要性があると認定された場合には、保育所などの利用料が無償化となります
次に高等教育の無償化、これは大学の入学金や授業料が減免になったり、奨学金がもらえたりする優遇措置になります。
以上が、必ず受けられる恩恵になります。
次に、それ以外の恩恵で主なものをまとめますと
④国民健康保険料の減免
これはお住まいの市区町村に申請することで、国民健康保険料が2割から7割までの減免する措置が受けられるということです。
因みに東京都23区内では、所得に応じて2割から7割の減額となっています。
⑤臨時の給付金
これは、国から臨時にさまざまな給付金が支給されることがあると言う話です。
例えば消費税増税の時は、住民税非課税世帯の人には「臨時福祉給付金」が支給されていました。
⑥その他
その他としては、入院中にかかる食事の自己負担額の減額、がん検診料金の免除、予防接種が無料といった優遇措置があります。
上記以外にも各自治体独自の優遇措置がありますので、詳しくはお住まいの市町村のHPなどで確認してみてください。
3.給与の金額(目安)は?
住民税非課税世帯となる年間の給与金額(前年の年収金額)の目安は、
①夫婦だけで生活している世帯
給与収入で156万円以下(所得ベースで91万円以下)
②夫婦と扶養親族が1人いる世帯
給与収入で206万円以下(所得ベースで126万円以下)
③夫婦と扶養親族が2人いる世帯
給与収入で256万円以下(所得ベースで161万円以下)
例えば、夫が主に稼いでいる場合だと、①は、夫の前年の給与が年間で156万円以下でかつ妻の収入は、住民税非課税レベルであった場合に、住民税非課税世帯になるということです。
なお、妻の収入が住民税非課税レベルであったというのは、つまり、妻は所得ベースでが35万円以下、給与ベースで言えば年間100万円以下の収入であったということですね。
因みにこの金額は、主に都市部に住んでいる場合の金額になります。
お住いの市区町村によっては、金額が若干異なってくる場合もありますので、目安と書かせていただきました。
この金額の根拠ですが、次の計算式に当てはめています。
35万円×(世帯人数)+21万円
なおこの計算式の「世帯人数」を正確に言うと、本人+控除対象配偶者+扶養親族の数という事になります。
4.年金の金額(目安)は?
今度は年金の目安金額になります。
住民税非課税世帯となる前年の年金額(目安)は、
①夫婦だけで生活している世帯
65歳未満は年金収入で約151万円以下
②夫婦だけで生活している世帯
65歳以上は年金収入が約201万円以下
因みにこの金額も、主に都市部に住んでいる場合の金額になりますので、目安と書かせていただきました。
例えば、夫の年金の方が多い場合、①は夫の年齢が65歳未満で前年の年金収入が年間で151万円以下であった、かつ 妻の収入も住民税非課税レベルであったという場合に、住民税非課税世帯になるということですね。
なお、妻の収入が年金収入のみの場合、住民税非課税レベルとなる年金の額は、
妻が65歳未満の場合は年間で約95万円以下、
妻が65歳以上の場合は年間で約145万円以下
ということになります。
5.年金額(目安)の根拠は?
まず夫婦だけで生活している世帯の場合、所得が91万円以下であることが、住民税非課税世帯の条件になっています。
これは、先ほど紹介した計算式【35万円×(世帯人数)+21万円】より計算しています。
つまり、夫婦二人生活していますから、ここには「2」が入ります。
従って、35万円×(2)+21万円=91万円ということですね。
次に年金額から所得を出すわけですが、令和2年の公的年金控除額を見ますと
1)65歳未満は60万円
2)65歳以上が110万円
ですので、①は年金収入151万円ー公的年金控除60万円=所得金額91万円
ということになり
②は年金収入201万円ー公的年金控除110万円=所得金額91万円
ということで、この金額が住民税非課税となる年金額ということになります。
#住民税非課税世帯 #年収 #年金
powered by Auto Youtube Summarize